2018年12月29日から2019年1月5日まで、イランを旅行してきた。8歳と6歳を連れての家族旅行である。全員イランは初めてだ。
2013年にインドから日本に戻って以来、大体2年に1回ぐらいのペースでインドの周辺国家を家族旅行してきた。2014年にはミャンマー、2016年にはウズベキスタンを旅行した。
これらの国々は、16世紀から19世紀にインド亜大陸で栄えたムガル朝と所縁の深い国々だ。ミャンマーのヤンゴンは、ムガル朝最後の皇帝バハードゥル・シャー・ザファル(1775-1862年)の葬られた都市である一方、ウズベキスタンには、ムガル朝の創始者バーバル(1483-1530年)の生まれ故郷フェルガーナや、その祖先のティームール(1336-1405年)が拠点としたサマルカンドがある。よって、ムガル朝はウズベキスタンから始まり、ミャンマーに終わると言ってよい。その間、現在のインドやパキスタン、そしてアフガニスタンを領土としながら盛衰してきた。よって、インド好きがウズベキスタンとミャンマーへ行く意味はあると考える。
そしてもし、もう一国、ムガル朝にとって重要な周辺国家を挙げるとしたら、それは間違いなくイランである。その理由はいくつかある。
言語学に「インド・イラン諸語」という用語があるように、現在インドで話されている言語の多くとイランで話されている言語の多くは、共通の祖先を持つと考えられており、民族的にもつながりが深いとされている。しかし、ここで注目したいのは、より歴史的なつながりだ。両国は、地理的に近接していることもあり、歴史的に互いに影響を与え合いながら発展してきた。
インドとイランの二国間関係史を考える上で、もっとも重要な出来事といえば、ムガル朝第2代皇帝フマーユーン(1508-1556年)のイラン亡命であろう。1530年に即位したフマーユーンは、東インドに興ったアフガン系王朝スール朝のシェール・シャー(1473-1545年)によって1540年に王権を奪われて以来、1555年にデリーを奪還するまで、15年間にわたって亡命生活を余儀なくされていた。その亡命生活の大部分を彼はイランで過ごした。サファヴィー朝のタフマースプ1世(1514-1576年)がフマーユーンを賓客として歓迎したからである。インド奪還に転じたフマーユーンは、 タフマースプ1世から軍事的支援を受け、 まずはアフガニスタンを支配下に治め、その後、後継者争いで混乱するスール朝を打ち破って、ムガル朝を再興した。このとき、多くのイラン人がフマーユーンに随行したとされる。フマーユーンはデリー奪還後すぐに事故死してしまうが、亡命中に生まれたアクバル(1542-1605年)が跡を継ぎ、ムガル朝を大帝国に発展させた。この亡命のおかげで、ムガル帝国は人的にも文化的にもイランの影響を強く受けるようになる。 現在、「インド文化」と見なされるものの多くは、このムガル朝期に成立しているため、イランがなければ今のインドもなかったと言えるくらい、イランはインドにとって恩人の国なのである。
サファヴィー朝とムガル朝はその後も友好国として良好な関係を保ち続けた。特にサファヴィー朝のアッバース1世(1571-1629年)とムガル朝のジャハーンギール(1569-1627年)は仲が良く、贈り物を交換し合っていた。例えば、1612年にアッバース1世はジャハーンギールにティームール・ルビーと呼ばれる361カラットの巨大なルビー(正確にはスピネル)を贈った。これは、ムガル朝皇帝の祖先ティームールが所有していたとされ、元々はティームールがインドを侵略したときに奪ったものだった。一方でジャハーンギールは1621年にアッバース1世にシマウマを贈った。動物好きだったジャハーンギールはエチオピアからシマウマを輸入していたのである。このように、長年両国は友好関係を保っていた。
他方で、ムガル朝の衰退もイランによってもたらされたと言ってもよい。ムガル朝は第6代皇帝アウラングゼーブ(1618-1707年)の時代まで強勢を誇るが、その後は指導力のある皇帝に恵まれず、衰退の一途を辿る。その隙を突いてインドに侵略してきたのが、サファヴィー朝の後に興ったアフシャール朝の創始者ナーディル・シャー(1688-1747年)であった。1739年、カルナールの戦いでムガル軍を打ち破った彼はデリーを占領し、略奪と殺戮の限りを尽くした後、イランへ戻って行った。このとき、ムガル朝の歴代皇帝たちが蓄えてきた財宝が奪い去られたが、その総額は、その後イランで税金が3年間免除になるほど巨額のものだったと言う。ナーディル・シャーの侵略によってムガル朝の衰退は決定的となり、以後、地方勢力の独立や、他勢力による支配や侵攻を許すことになる。
イランは現在、シーア派のイスラーム教徒が多数を占める国家であるが、イスラーム化以前はゾロアスター教が広く信仰されていた。ゾロアスター教を国教としたサーサーン朝(226-651年)が7世紀にイスラーム帝国との戦いに敗れ、滅亡すると、多くのゾロアスター教徒たちが改宗や殺害から逃れるためにインドへ渡ったとされる。現在でもイランには25,271人(2011年国勢調査)のゾロアスター教徒が残っているが、その2倍以上の57,264人(2011年国勢調査)がインドにおり、経済的に非常に成功したコミュニティーとしてインド社会に溶け込んでいる。ゾロアスター教にとって、インドは第二の故郷と言ってよく、インドとイランの歴史的つながりの重要な一要素だ。
現在、イランで公用語として使われているのはペルシア語だが、インドは政治や文学において、ムガル朝成立以前からペルシア語の影響を色濃く受けてきた。ペルシア語と一口に言っても、各時代で様々な形があるが、イラン系民族のイスラーム化以降、アラビア文字で書かれるようになったものを近世ペルシア語と呼んでおり、ここで話題としているのもそれである。ペルシア語は10世紀頃に中央アジアで政治や文学の主役となり、周辺地域に広がって行った。結果、ペルシア語を共通語もしくは教養語とする「ペルシア語文化圏」がユーラシア大陸一帯に形成された。13世紀以降、ペルシア語を話すトルコ系民族によって主に支配されてきたインドもその文化圏に組み込まれた。以来、19世紀に英語に取って代わられるまで、インドで記録や文芸の第一の担い手となってきたのはペルシア語だった。現在、インドの連邦公用語となっているヒンディー語にも多くのペルシア語彙が流れ込んでいる。ヒンディー語にとってのペルシア語は、ちょうど日本語にとっての中国語のような存在だ。ヒンディー語学習者であれば、ペルシア語の本拠地であるイランへの憧憬は自然と育まれるものである。
というわけで、単なる旅行記ではなく、「インド」という視点を混ぜながら、今回のイラン旅行を振り返ってみたいと思う。
ヴィザ
イランに渡航する際には査証が必要になる。空港でアライヴァル・ヴィザも取得できるが、ヴィザ取得も旅行の一種と考えているので、イラン大使館で事前に観光ヴィザを取得することにした。ただし、イラン大使館のある東京まで申請と受領のために2度も足を運ぶ時間がなかったため、郵送での申請となった。
イラン大使館のウェブサイトに詳しく書いてあるので、それをよく読んでその通りにすれば、まず間違いなくヴィザを取得できるだろう。僕が申請した2018年12月時点での手続きでまず行ったことは、e-Visaのウェブサイトへ行って必要事項を記入し、送信することだ。この際、顔写真とパスポートの画像ファイルや現地滞在先(ホテルなど)の住所などが必要となるので、予め用意しておく。そうすると、登録したEメールアドレスに、申請が受理された旨のEメールが届いた。翌日、もう1通メールが届き、ヴィザの発給が認められた旨を知らされた。PDFファイルが添付されているので、これをプリントアウトする。これを①とすると、②大使館のウェブサイトからダウンロードしたアプリケーションフォームに必要事項を記入し顔写真を貼付したもの、③有効期限が6ヶ月以上あるパスポート、④ヴィザの代金をイラン大使館の銀行口座に振り込んだ際に発行される振込証明書原本(郵送の場合のみ必要)、そして⑤返信用のゆうパック(郵送の場合のみ必要)と一緒に大使館にゆうパックで送る。そうしたら、前回のメールから3日後にヴィザが発行された旨のEメールが届き、それから数日内にパスポートとヴィザがゆうパックで送られてきた。
ヴィザは、他国のヴィザと異なり、パスポートに貼られたり、スタンプを押されたりする形ではなく、A4判の1枚の紙であった。イラン滞在中はパスポートに加えてこの紙を紛失しないように持っていなければならないので、多少面倒である。
実は、2011年3月1日以降にイランに渡航した経歴を持つ日本人は、米国入国の際に電子渡航認証システム(ESTA)が使えなくなる。ESTA登録時に「2011年3月1日以降、イラク、シリア、イラン、スーダン、リビア、ソマリアまたはイエメンに渡航または滞在したことがありますか?」という質問項目があり、これが「はい」になってしまうと、ESTAでの認可は下りなくなるようだ。ESTAはヴィザ免除プログラムである。つまり、イランに1回でも渡航してしまうと、現時点では生涯、米国渡航時にヴィザ免除が認められず、事前にヴィザ取得の手続きを踏まなければならなくなる。近々米国に行く予定はないので、現時点ではあまり気にしていないが、将来的にちょっとした障害になり得る。ヴィザが別紙になっているのは、もしかしたらパスポートにイラン入国の記録が付かないようにする配慮かもしれない。パスポートには出入国スタンプすら押されず、イランに入国した痕跡は全く残されないので、ESTAの登録時に嘘をついて上記の質問項目を「いいえ」にすれば、ESTAは通るかもしれない。だが、米国のことなので、どこでどういう情報を入手しているか分からず、危ない橋を渡ることになりかねない。ヴィザ取得は、慣れてしまえば楽しい手続きなので、この際、普通の日本人は持つ必要のない米国観光ヴィザ(10年有効)を取得しておくのもいいかもしれない。
また、出入国審査の際にパスポートと一緒にヴィザの紙も出したが、係員はその紙を見ようともしなかった。各渡航者の査証情報はパスポート番号で管理されていて現物は必ずしも必要ないのかもしれない。ただし、一部のホテルではチェックイン時にパスポートに加えてヴィザの紙の提示も求められたので、持参する必要はあるだろう。
旅行情報
イランには成田空港からドーハ経由で行った。行きの飛行機は成田22:20発のカタール航空QR807(JL7995とコードシェア)で、ドーハには翌日5:00着。日本とカタールの時差は6時間あるので、およそ13時間のフライト。そこからドーハ8:00発のQR482に乗り換え、テヘラーンのイマーム・ホメイニー国際空港には同日の10:40着。ドーハとテヘラーンの時差は30分で、およそ2時間のフライト。帰りの飛行機は、テヘラーン22:50発のQR499で、ドーハ着は翌日の0:30。やはり2時間ほどのフライトだ。ドーハからは1:55発QR806(JL7994とコードシェア)に乗り換え、同日17:55に成田着。偏西風の影響で行きよりもフライト時間は短く、10時間ほど。さらに、実際には30分早く着いた。
カタール航空は初めて利用したが、非常に良かった。成田~ドーハ便ではエコノミークラスでもアイマスクや耳栓などがセットになったアメニティがもらえたし、どちらの便でもキッズミールや子どもたちへのプレゼントが充実していた。当然、各座席に端末が付いていて、映画やゲームなどで時間を潰すことができた。個人的にはインド映画のラインナップが豊富だったのがありがたかった。最新作のカテゴリーでは2017年から2018年前半あたりの作品が中心で、もっとも新しいのは2018年8月公開の「Nawabzaade」(2018年)だった。機内食も全体的に悪くなかった。なぜか毎回ゴディバのチョコレートが付いてきた。試してはいないが、離陸後はWiFiも利用できる。また、ドーハ~テヘラーン便は利用客が少ないのか、とても空いていたので、リラックスできた。
イランでの旅程は以下の通りである。かなり忙しい日程だったが、後から考えて外した方が良かった都市はひとつもないので、忙しさを解消するためには日数を増やすしかないだろう。
- 1日目:テヘラーン空港着、専用車でテヘラーン観光、夜 国内線でシーラーズへ、シーラーズ泊
- 2日目:午前中 シーラーズ、ペルセポリス観光、午後 専用車でヤズドへ、ヤズド泊
- 3日目:午前中 ヤズド観光、午後 専用車でイスファハーンへ、イスファハーン泊
- 4日目:終日 イスファハーン観光、イスファハーン泊
- 5日目:午前中 専用車でアブヤーネへ、午後 専用車でコムへ、その後テヘラーンへ、テヘラーン泊
- 6日目:終日 専用車でテヘラーン観光、夕方 テヘラーン空港へ
シーラーズではKarim Khan Hotel、ヤズドではDad Hotel、イスファハーンではSetareh Hotel、テヘラーンではTehran Enghelab Hotelに宿泊した。この中でもっとも良かったのはヤズドのDad Hotel。広い中庭を囲んで四方に客室が並んでおり、この地方の伝統的な邸宅の様式となっている。部屋も広く、快適な滞在であった。意外に悪かったのがTehran Enghelab Hotelだ。高層の都会型ホテルで、規模はもっとも大きかったのだが、部屋はそれほど広くなく、最上階に近い15階の部屋だったためかシャワーやトイレの水圧が低くて、バスルームが使いにくかった。
全体として天候には恵まれず、シーラーズ、ペルセポリス、アブヤーネは雨天の中での観光となり、コムは強い雪のために大事を取って立ち寄らなかった。ヤズドと最終日のテヘラーンは快晴だった。
前々回のミャンマー旅行、前回のウズベキスタン旅行と同様、旅行の手配は西遊旅行に依頼した。スルーガイド付きで、ほとんどが専用車での移動なので、楽には楽だったが、おかげでイランの交通情報には長距離移動・市内移動共に暗いままだ。また、宿泊費や食費は事前に支払い済みで、その他の追加的な支払いも基本的にはガイドがカードで立て替え払いをしてくれたので、お土産以外に現地の通貨を使う機会はほとんどなかった。
イランの通貨単位はリアル(Rls)。公式レートでは1ドルが42,000リアルほどである。ただし、これは銀行で両替した場合のレートであり、両替屋で両替すると、1ドルが100,000リアル以上になる(闇両替ではない)。リアルとドルの両方で支払える土産物屋では、100,000リアル=1ドルという計算のようだったから、銀行で両替すると損にしかならない。必ず両替屋で両替すべきである。イマーム・ホメイニー国際空港では、税関を抜けて到着ロビーに出た先にあるエスカレーターを上った2階に両替屋がある。
また、外国人にとって大いに混乱の種が、イランではリアルの他にトマーン(T)という単位もよく使われていることだ。1トマーン=10リアルである。そして、店などではこちらのトマーンの方がよく使われている。しかも、桁数が大きすぎるためか、トマーンを1,000で割った額も便宜的にトマーンとして使う。非常にややこしいのだが、最高額紙幣である緑色の10万リアル札が1万トマーンで、これが10トマーンと呼ばれることもあり、さらにこれが1ドルまたは100円とほぼ同等と覚えればある程度は分かりやすかった。オシャレなカフェで紅茶やコーヒーを飲むと、大体10トマーン(=10,000トマーン=100,000リアル=100円)から20トマーン(=20,000トマーン=200,000リアル=200円)ぐらいの値段だった。物価は非常に安いと言える。
イランではキャッシュレス化が進んでおり、カードでの支払いが主だった。しかし、使えるのはイランの銀行が発行するカードのみで、外国で発行されたクレジットカードやデビットカードは使えないので、一時的な滞在者は現金払いを余儀なくされる。また、両替できるのは米ドルかユーロのみだ。よって、イランを旅行する際、必要な分の現金を米ドルかユーロで持参する必要がある。
通信事情は悪くなかった。今回、現地の大手通信会社MTN IrancellのSIMカードをSIMフリーのiPhone 6sに入れて使用した。イマーム・ホメイニー国際空港のMTN Irancellカウンターでも購入可能だったが、ガイドが用意してくれていたので、それを貸してもらった。5GBをチャージして210,000リアルだった。都市部ではLTE(4G)でネットができたが、郊外では3Gもしくはそれ以下の電波しか来ていないところもあった。また、ホテルにはWiFiがあった。イランではFacebookやTwitterなどが規制されていて使えないとされているが、VPNを使えば簡単にそれらに接続ができ、画像などをアップロードすることができた。ちなみに僕はVPNネコというアプリを利用した。結局、概ねネットで不自由しない国であった。
光の海
インドつながりで、イランでもっとも見てみたかったものは、ダリヤーエ・ヌールであった。
18世紀まで、インドはダイヤモンドの唯一の生産国であった。よって、それまでにこの世に出現した全てのダイヤモンドはインド産と断言してよい。名前を付けられた世界的に有名なダイヤモンドの多くがインド産なのも無理はない。なお、現在、インドのダイヤモンド産出量は減少したが、ダイヤモンド研磨・加工業は主要産業として残っており、世界一の規模を誇っている。
歴史上、もっとも有名なダイヤモンドはコーヘ・ヌール(コーヒ・ヌール)であろう。「光の山」と名付けられたこの186カラットの巨大なダイヤモンドは、間違いなくインド産であり、16世紀に初めてこの名前で文献に登場して以来、ムガル朝皇帝の所有物だった。ところが、18世紀にナーディル・シャーの侵略によって奪われ、その後、アフガニスタンに興ったドゥッラーニー朝のアハマド・シャー・アブダーリー、パンジャーブ藩王国のランジート・スィンなどの手を転々としながら、最終的に英国ヴィクトリア女王の所有物となった。その後、ブリリアントカットにカットされ、重さは105カラットになったが、輝きは増した。現在は英国王室の女王の王冠に収められており、ロンドン塔のジュエル・ハウスで展示されている。
そのコーヘ・ヌールと姉妹のダイヤモンドともいえるのが、ダリヤーエ・ヌール(光の海)である。希少なピンクダイヤモンドで、元々は242カラットあったとされる。やはりムガル皇帝の所有物で、ナーディル・シャーによって奪われた後、2つにカットされ、現在は182カラットになっているが、それでも世界最大のピンクダイヤモンドである。このダリヤーエ・ヌールがイランの国立宝石博物館に収められている。
イランが誇る数々の宝石・貴金属・装飾品類が収められたこの博物館は、テヘラーンのイラン中央銀行の地下にある。イランでもっとも厳重な警戒態勢が敷かれており、中には何も持って入れない。本当は12歳未満の子供も入場できなかったが、ガイドが交渉してくれた結果、子供も入れてもらえた。意外に融通が利くことに驚いた。いかにも金庫の扉といった感じの分厚い扉の奥には薄暗いホールがあり、そこに数十のショーケースが整然と並んでいた。展示物の多くはイランの歴代王朝が使用してきた、宝石を散りばめた装身具や調度品等だが、それに加えて、新たにアクセサリーの素材にするつもりだったのか、ダイヤモンド、ルビー、エメラルド、トルコ石といった宝石が、ショーケースのあちこちに、まるでビー玉かキャンディーのように、無造作に山積みされていた。
目当てだったダリヤーエ・ヌールは、ホールに入ってすぐ、正面のショーケースに展示されていた。想像していたものよりも小ぶりで、ガイドから指摘されなければ見過ごしていたかもしれない。457個の小粒ダイヤモンドと4個の小粒ルビーが散りばめられたフレームに収められたダリヤーエ・ヌールは長方形をしていて、表面はヌルッとした光沢を持っていた。ダイヤモンドといえばゴツゴツしているというイメージを持っていたので、形からも珍しさを感じた。また、色は確かにピンクがかっているが、ダイヤモンドの色としては非常に希少であるらしい。カージャール朝(1789-1925年)やパフラヴィー朝(1925-1979年)の皇帝がターバンの飾りとして使って来たようだ。
このダリヤーエ・ヌールは元々、ムガル朝の玉座である孔雀の玉座にはめ込まれていたらしい。孔雀の玉座とは、タージマハルを建造したことで知られるシャージャハーン(1592-1666年)によって造られた、1150kgの金と230kgの宝石で装飾された豪華絢爛な椅子である。孔雀の玉座には、ダリヤーエ・ヌールの他に、前述のコーヘ・ヌールやティームール・ルビーも埋め込まれていた。一説によると、この玉座の価格は、大理石でできた巨大な墓廟であるタージマハルの総工費の2倍もしたらしく、そのとてつもない価値がうかがわれる。デリーのラール・キラーにあるディーワーネ・カース(貴賓謁見の間)に安置され、ムガル皇帝の権力の象徴であった。ところが、ダリヤーエ・ヌールはナーディル・シャーによって孔雀の玉座ごと奪われ、抜き取られた。コーヘ・ヌールとティームール・ルビーの所在地はアフガニスタン、インド、そして英国へと移り、現在はエリザベス女王の所有物となっている。一方、ダリヤーエ・ヌールはイランに残った。
孔雀の玉座は、インドから持ち去られ、コーヘ・ヌールなどの希少な宝石類が抜き取られた後、イラン北東部のカラートに保管されていたようだ。カラートはナーディル・シャーの生まれ故郷の近くだった。1747年、ナーディル・シャーはカラートに戻るが、そこで宿営しているときに暗殺され、孔雀の玉座は略奪者たちによって解体され持ち去られてしまう。このとき、ナーディル・シャーの後宮の護衛を務めていたアフガン系軍人のアハマド・シャー・アブダーリーは、混乱の中で後宮のテントを守り切り、ナーディル・シャーの第一夫人から褒美としてコーヘ・ヌールとティームール・ルビーを与えられた。彼は故郷に戻った後、ドゥッラーニー朝を興し、現在のアフガニスタンの礎を築いたのだった。
国立宝石博物館には「孔雀の玉座」も展示されているが、これは、カージャール朝のファテ・アリー・シャー(1772-1834年)によって再建されたもので、インドから持ち去られたものではない。それでも、宝石が散りばめられ、黄金に輝く、美しい玉座だ。これが「孔雀の玉座」と呼ばれるようになったのは、ファテ・アリーの妻の1人がターウース(孔雀)という名前だったからのようである。ちなみに、ファテ・アリーには1,000人以上の妻がおり、子供の数も100人以上だったとされる。ターウースはその中でもお気に入りだったようだ。
他にも多くの財宝が国立宝石博物館に収められている。宝石があまりにふんだんに使われ過ぎていて、そして展示品の数が多すぎて、だんだん感覚が麻痺してくるが、ひとつひとつ非常に高価な品なのは間違いない。それらがこれだけ一堂に会しているのだから、一体この博物館の展示物の総額はいくらになるのだろうか。ダリヤーエ・ヌール以外で特に印象深かったのは、宝石で装飾された地球儀であった。34kgの金と、重さ3,656g、合計51,366個の宝石で構成されたこの逸品は、エメラルドで海が、ルビーで陸が表現され、いくつかの国はダイヤモンドやサファイヤで示されている。
国立宝石博物館の展示物の質と量に大いに驚いたが、それ以上に驚きだったのが、これらの宝飾品類が近現代イラン史の様々な混乱期をくぐり抜けて今日まで残っていることである。歴代王朝の度重なる崩壊や内紛、欧米列強の進出や革命などを経て今のイラン・イスラーム共和国がある訳だが、混乱期には略奪や暴動もあっただろうに、これだけの宝石や貴金属が無事に保管されているのは、奇跡としか言いようがない。
世界の半分
インドの首都ニューデリーにおいて現在オールドデリーと呼ばれている地区は、かつてシャージャハーナーバードと呼ばれていた。ムガル朝第5代皇帝シャージャハーンによって建造され、1648年に落成した城塞都市であり、ヤムナー河の西岸に寄り添っている。「リッジ」と呼ばれる弓状に広がる丘陵地帯と、その弦となるヤムナー河に囲まれた三角地帯には、13世紀にイスラーム政権が打ち立てられて以来、いくつもの城塞都市が造られ、それぞれの王朝の首都や重要拠点となってきたが、これらが全て「デリー」と呼ばれきた。シャージャハーンは、全く新しい都市を、それら全ての北、リッジの北端とヤムナー河の接点付近に造り出した。この都市を設計する上でシャージャハーンが強く意識したのが、「世界の半分」と賞賛されるまで栄華を極めたイスファハーンであったとされる。
イスファハーンの、町としての歴史は紀元前まで遡れるが、イスラーム教政権の支配下に入ってから、複数の王朝の首都となったことで、都市として、そして交易の中心地として、発展してきた。特に11世紀に興ったセルジューク朝の首都となってから繁栄するが、その後はモンゴル帝国やティームール朝などの度重なる侵略を受け、何度も衰退を経験した。そのような荒廃の時代を乗り越え、イスファハーンが見事に再生して、最盛期を迎えるのが、サファヴィー朝のアッバース1世の時代である。1597年にイスファハーンはサファヴィー朝の首都となる。
イスファハーンの発展が刻まれた史跡がある。旧市街にあるマスジド・ジャーメ(金曜モスク)である。イスラーム都市にとって、王権と結びつき、市民の信仰の中心でもある金曜モスクは、もっとも重要な施設であり、真っ先に投資がなされる。イスラーム教徒は金曜日にモスクで集団礼拝を行うが、多くの場合、各都市の中心部に設けられ、その都市で最大規模を誇る金曜モスクは、その際に中心的な役割を果たす。また、金曜モスクで金曜日に支配者の名の下で説教を行うことが、その都市の支配権を確立、または維持していることを示す。
イスファハーンのマスジド・ジャーメは元々、ゾロアスター教の寺院があった場所に8世紀に建造されて以来、この街を支配した各王朝が拡張工事を繰り返してきたため、各時代の建築様式が混ざり合っている。当然、拡張工事の理由は人口の増加であろう。マスジド・ジャーメでもっとも古い部分は、入り口から入ってすぐ左にある、小ぶりのドーム天井を支える柱が林立するホールである。柱が立ち並ぶ多柱式の礼拝堂は、最初期のモスクに特徴的であり、元々はアラブ地方の様式とされる。ウズベキスタンのヒヴァのジュマ・モスクも同様である。
ただ、イスファハーンのマスジド・ジャーメは、歴代王朝による増改築が繰り返される中で、中庭を中心として、東西南北からイーワーンによって囲まれた様式、いわゆるチャハール・イーワーン様式のモスクへと発展していった。イーワーンとは、一方が完全に開き、三方が壁で囲まれ、天井がアーチ状となったホールのことで、イスラーム建築の特徴のひとつである。時代が下るごとにイーワーンの使われる数が増えていき、やがて4つのイーワーンが中庭を囲むチャハール・イーワーン様式が完成したが、イスファハーンのマスジド・ジャーメはその現存最古の例とされる。イスファハーン史のみならず、イスラーム建築史においても重要な史跡だ。ちなみに、現在もモスクとして使われている。
かつてのイスファハーンは、このマスジド・ジャーメを中心に市街地を形成していた。アッバース1世はイスファハーンを首都に定めると、南を流れるザーヤンデ河と旧市街の間に新たな計画都市を建設した。その中心となったのがイマーム広場である。長さ512m、幅163mの、南北に長い、長方形の広場で、アーケードによって四方を囲まれている。その広さは世界最大規模で、有名なヴェネツィアのサンマルコ広場の7倍の広さを誇る。現在この広場は壮麗な噴水を擁したヨーロッパ風の美しい庭園となっているが、かつては更地で、時々ここでポロの競技が開催されたという。ポロのゴールポストも残っている。
広場の東には、元々マドラサ(神学校)だったとされるモスク、マスジデ・シェイフ・ロトフォッラー、西には皇帝の宮殿だったアーリー・カープー宮殿、南にはブルータイルで装飾されたドームを持つ巨大なマスジデ・シャーが建ち並び、サマルカンドで見たレーギスターン広場を思い出させた。
広場の北には天井付きのバーザールの入り口があり、これは延々と旧市街のマスジド・ジャーメ前のコフネ広場までつながっている。イマーム広場周辺や、旧市街まで連なるこのバーザールには、世界各地から集められた一級の職人たちの工房や世界各地の特産品を扱う商人たちの店が並んだ。その様子から、この広場はかつて「ナクシェ・ジャハーン」、つまり「世界地図」と呼ばれた。現在、イマーム広場を囲むバーザールでは、観光客向けに、絨毯、陶器、エナメル製品、細密画、タイル、貴金属、織物などの店が並んでおり、北側のバーザールへ行くとより地元民向けとなって、生活雑貨などを扱う店舗が増える印象だった。
イマーム広場の西には、南北を縦断し、ザーヤンデ河に架かる橋を越えて向こう岸まで通じるチャハール・バーグ通りが建造された。チャハール・バーグとは、イランの庭園に特徴的な四分庭園である。この通りはその名の通り、通りの中心に水路が通され、水路を挟むように街路樹等が植えられ庭園を形成し、その外側に道が通るという、庭園と大通りが一体となった作りをしている。今でこそ珍しくないコンセプトではあるが、当時としては革新的であったらしく、その美しい景観は世界に喧伝された。
デリーのシャージャハーナーバードには、東西に横断し、皇帝の居城だったラール・キラーの門まで通じるチャーンドニー・チョウクという大通りがある。現在は何の色気もない喧噪のバーザールとなっているが、シャージャハーンの長女ジャハーナーラーが造ったこの通りはかつて、中心に水路が通され、街路樹が植えられ、通りの中心に設けられた広場には月の光を映す池が設けられ、非常に美しい市場だったという。この通りのモデルとなったのがイスファハーンのチャハール・バーグ通りだったとされる。
もっとも、イスファハーンの都市計画とシャージャハーナーバードの都市計画に、多くの共通項があるわけではない。例えば、 シャージャハーナーバードはヤムナー河の西岸に建造され、イスファハーンはザーヤンデ河の北岸に建造されたが、共通しているのは河のそばにあることのみで、都市構造は全く異なる。シャージャハーナーバードでは皇帝の居城が河のそばにあるが、イスファハーンでは河から離れた場所にイマーム広場などが設けられている。また、イスファハーンでは、長い長いアーケードによって旧市街と新市街が結ばれているが、シャージャハーナーバードにそれは見られない。シャージャハーナーバードでアーケードを持つバーザールは、ラール・キラー内のチャター・チョウクくらいだ。さらに、シャージャハーナーバードにはいくつもの庭園があったが、イスファハーンのイマーム広場のような巨大な広場兼バーザールがあった痕跡はない。
あくまでシャージャハーンは、遠く離れたイスファハーンの評判を聞き、それを越える都市空間の創出を目指したのであり、イスファハーンそのものをモデルにしたわけではないだろう。唯一、チャーンドニー・チョウクの原型には、チャハール・バーグ通りの直接的影響を見出すことが可能である。
イスファハーンには、上記以外にインドとのつながりを示すものも見つけた。それは、イマーム広場の西にあるチェヘル・ソトゥーン(40本の柱)という宮殿だ。1647年に、アッバース1世の曾孫にあたるアッバース2世(1632-1666年)によって建設された迎賓館で、周囲は庭園となっている。かつてはイマーム広場に面したアーリー・カープー宮殿と接続されていた。屋根を支える柱は20本のみだが、なぜ「40本の柱」と呼ばれるかというと、その前面にある池に柱が映り、合計40本になるからだ。同様の仕掛けの建築物はウズベキスタンのブハーラーでも見た。ボロ・ハウズ・モスクである。ただし、ブハーラーのモスクは1712年に建造されているため、イスファハーンの方が古い。関連があるかは不明である。
このチェヘル・ソトゥーン内部の内壁には巨大な壁画が6つ描かれている。これらの壁画がいつ誰によって描かれたのかについては、少し調べてみたが分からなかった。だが、チェヘル・ソトゥーン完成後の出来事を描いた壁画もあることから、建物の建築年とは一致していないだろう。
この6つの壁画の内、2つはインド関係だ。入って正面左にあるのは1544年にタフマースプ1世がフマーユーンの亡命を受け入れ、もてなしている場面だ。中央奥で2人が座って向かい合い、両隅には家臣らしき人々が控えている。イランの楽師たちが音楽を奏で、長髪で色白の踊り子たちが舞を興じている。おそらく中央奥の左、色黒に描かれている方がフマーユーンであり、その後ろにいる人々が彼の家臣であろう。亡命中であることを示すみすぼらしさや後ろめたさは絵から感じないが、フマーユーンの方がターバンの飾りが少なく、フマーユーンの家臣たちの表情に若干の不安が見られる。しかしながら、わざわざこの場面を、実際の出来事があってから100年以上後に壁画にするということは、イラン側もムガル皇帝の亡命を名誉なことと捉えていたと考えていいだろう。
もうひとつのインド関係の絵は、入ってすぐ後ろを振り返ると目に入ってくる、戦争のシーンを描いた壁画である。これは、アフシャール朝のナーディル・シャーとムガル朝のムハンマド・シャーが戦った1739年のカルナールの戦いを描いたものだ。ナーディル・シャーは兵力で劣っていたが、軍事の天才である上に、ラクダと銃火器を組み合わせた、ザンブーラクという現代の戦車にあたるような新兵器を活用していた。一方のムガル軍は象兵でゴリ押しする古い戦略を用いており、しかもアワド太守とデカン太守の仲違いが進行していた。勝敗はあっけなく決まり、ムハンマド・シャーは降伏する。ナーディル・シャーはムハンマド・シャーと共にデリーに入城し、当初は礼儀正しく振る舞っていた。だが、「ナーディル・シャーが暗殺された」とのデマを信じたデリー市民がペルシア軍に襲いかかり、多数の死者が出たことに腹を立て、報復の大虐殺を命じた。デリーは、1398年のティームールによるデリー侵略以来の虐殺を受け、3万人の市民が殺されたという。イラン側にとっては完勝であるこの戦いを誇らしげに宮殿に壁画に描くのは理解できる。中央左で馬にまたがり、一際大きく描かれているのがナーディル・シャーで、中央右の方で象に乗っているのがムハンマド・シャーである。アラビア文字で名前が添えられているので確実だ。他にも将軍たちらしき人々の名前が書かれているが、史実と一致する名前は見つけられなかった。
絹糸の民
イスファハーン南部をザーヤンデ河が流れている。最近、イランでは気候変動のためか降水量が少ないらしく、また、水資源の乱用があるようで、我々が訪れたときには、ザーヤンデ河は干上がってしまっていた。
ザーヤンデ河の南岸にはジョルファーという地区がある。アッバース1世は、イスファハーンを新首都と定め、新都市の建造に取りかかった後、1605年にアルメニア人を呼び寄せ、もしくは強制的に移住させ、このジョルファー地区に住まわせた。
アルメニアは、黒海とカスピ海に挟まれた、イランの北にある小国で、古代から中世にかけて、イランに興った王朝の支配下に度々置かれており、イランとはつながりが深い。世界でもっとも早くキリスト教を国教とした人々で、世界中にネットワークを持っており、ユダヤ商人を凌ぐ商才で知られる。アルメニア人が特に得意としたのが絹糸の貿易で、17世紀には世界の絹糸貿易の7割を牛耳っていたとされる。他にダイヤモンドや宝石の貿易にも関わっていた。アッバース1世は、アルメニア商人の世界的ネットワークを借りて、イスファハーンを国際貿易のハブ都市としようとしたのである。よって、ジョルファー地区に移住したアルメニア人には、信仰の自由などの特権が与えられていた。
ジョルファー地区には現在でも1万人以上のアルメニア系イラン人が住んでいるという。この地区にはいくつもの教会が建ち並んでいるが、中でももっとも有名なのはヴァーンク教会である。ジョルファー地区へのアルメニア人の移住が始まった頃から建設が始まり、17世紀の中頃に完成したとされる。外観はドームを載せたモスク風の建物だが、中は十字架を掲げた教会となっている。大工が、教会を見たことがないイラン人だったために、この折衷様式が生まれたのであろう。内壁には金箔がふんだんに使われた豪華絢爛な壁画が描かれており、最後の晩餐や天国地獄絵図などが描かれている。画風は、チェヘル・ソトゥーン宮殿のものとよく似ている。また、敷地内には博物館があり、オスマントルコによるアルメニア人虐殺を中心に展示があった。
実はアルメニア人はムガル朝時代にインドにも拠点を持っており、デリーやアーグラーなどの内陸都市や、カルカッタ、マドラス、スーラト、ボンベイなどの港町にアルメニア人の居住区があった。これらインドに移住したアルメニア人の故郷は、ほぼイスファハーンのジョルファー地区であった。
ムガル朝の宮廷にもアルメニア人がいた記録がある。例えば、アクバル(1542-1605年)の妻の一人はマリアムという名のアルメニア人だったとされるし、彼はアブドゥル・ハーイーというアルメニア人を裁判長に任命した。また、彼は後宮の医療のためにジュリアナというアルメニア人女医を召し抱えていた。アクバルの時代の首都だったアーグラーには、彼によって1562年にインド初のアルメニア正教会が建てられた。
しかしながら、ムガル朝の歴史にもっとも影響を与えたアルメニア人といえば、ムムターズ・マハル(1593-1631年)をおいて他にないだろう。本名をアルジュマンドというこの絶世の美女は、イランからインドに移住してきた名門貴族の娘で、アーグラーで生まれたが、その祖先を辿っていくと、アルメニア系だという説がある。アルメニアとインドの地理的な距離を見るとすぐにはピンとこないが、イスファハーンのジョルファー地区を介して多数のアルメニア人がインドに来ていたことを知れば、ムムターズがアルメニア系イラン人の家系であることに大きな疑問は沸かないだろう。1612年にムムターズはシャージャハーンの2番目の妃になるが、彼女は皇帝の寵愛を一身に受け、1631年に38歳の若さで亡くなるまで、14人の子供を産む。ムムターズを失ったシャージャハーンは深く悲しみ、彼女のために22年をかけて世界一美しい墓を造る。それがアーグラーのタージマハルであり、現在まで旅行者を魅了して止まない。
ちなみに、アルメニアは世界に名だたる美人大国のひとつとして名高い。アルメニア本国に行けば確実であろうが、イスファハーンのジョルファー地区でも、シャージャハーンを虜にしたムムターズの面影を、今でも見つけることができる。
宴の町
イランの観光地でもっとも人気が高いのは、シーラーズから北東に60kmの地点にある古代遺跡ペルセポリスだという。ヨルダンのペトラ遺跡、シリアのパルミラ遺跡と並んで、「中東の3P」の一角を形成する。紀元前550年にキュロス2世によって興されたアケメネス朝の都市のひとつで、紀元前520年にダレイオス1世によって建設が始まり、その次のクセルクセス1世の時代に完成した。当時、世界最大の帝国となったアケメネス朝の首都は、スーサ、エクバターナ、バビロンなどに置かれたようで、ペルセポリスはイランの新年であるノウルーズを祝うための儀礼用の都市だったとされる。ただし、アケメネス朝に侵略したアレクサンドロス大王が紀元前331年に わざわざこのペルセポリスを攻撃し破壊していることや、スサを上回る黄金をペルセポリスで略奪していることから、何らかの重要性を持つ都市だったことがうかがわれる。かつて、「太陽の下でもっとも栄えた都市」と形容されるほどの隆盛を誇ったとされるが、アレクサンドロス大王の破壊もあって、現在では廃墟となっている。
ペルセポリスの遺跡入り口に立つと、正面の山の麓に、いくつもの柱が立った高いプラットフォームが目に入ってくる。近づくと、それが石を積んで人工的に組み立てられたものであることが分かってくる。地上から10m以上の高さはあり、総面積は12万5千平方mある。日本の石垣とは違って、立方体状の石が非常に精緻に組み合わされており、その技術の高さに驚かされる。
プラットフォームの西側に設けられた階段を上ると、いよいよペルセポリスの遺構が眼前に広がる。まずは「万国の門」と呼ばれる門の跡がそびえ立っている。西口の両側には牡牛像の跡が残っており、門の中に入るとホールになっている。ホールを越えて出ると、今度は東口の両側にメソポタミア文明に特徴的なラマッス(人頭有翼獣)像の跡が彫られている。この門は待合ホールのような機能を果たしたらしく、来訪者はここで指示を待ったようだ。
万国の門の南にはアパダーナと呼ばれる謁見の間がある。2.6mの高さのプラットフォームの上に、かつては30本の高さ20mの柱によって屋根が支えられた巨大な宮殿が建っていた。ここでナウルーズの祭礼を行ったり、属国の使者たちに謁見したりしたようだ。
アパダーナの階段にはレリーフがよく残っている。特に東階段のレリーフは保存状態がいいため、特別に屋根が設けられて保護されている。そこには、23の属州から使者が贈り物を持ってペルセポリスを訪れる様子が描かれている。それらの地域はほぼ特定されており、西はギリシアやリビア、東はインドやガンダーラ、北はアルメニアやウズベキスタン、南はアラビアやエチオピアまで及び、アケメネス朝の版図と一致している。それぞれの使者は現地の特徴的な服装を身にまとっており、各地の特産品を持参している。それはまるで万国博覧会のようである。アケメネス朝は、世界初の大帝国だっただけでなく、支配下に置いた地域や民族に対して寛容な政策を採ったことでも知られている。この「万国の階段」は、そんなアケメネス朝の宥和政策をよく象徴している。
やはりインドからの使者が気になるわけだが、それは東階段の南側の、三列に使者の彫刻が並んでいる部分の、一番左下に位置している。
アケメネス朝の官僚組織で中心的役割を担っていたペルシア人とメディア人の2人の官僚に続いて、4人のインド人が歩いている。上半身は裸で、下半身には腰布を巻いており、頭には鉢巻きのようなものを巻いている。「インド」と言ってはいるが、正確にはスィンド地方の人々のようで、現在はパキスタンになる。馬のような動物を連れているが、気になるのは一番前の者が天秤棒にぶら下げている壺の中身だ。ガイドの話では、この中にはスパイスが入っているとのことだったが、調べてみたところ、この中には砂金が入っている可能性が高いようだ。確かにスパイスだけだったら、献上品にしては量が少なすぎる。
果たしてスィンド地方で砂金が取れたか、ということだが、これはヘロドトスが「歴史」で記した、「金を掘り出す蟻」と関係しているかもしれない。ヘロドトスは、インド北方に、「犬よりは小さく狐よりは大きい」蟻がいて、地中から砂金を掘り出すと書いている。その後の研究により、これは蟻ではなくマーモットで、実際に印パ国境近くに、マーモットに地中から砂金を掘り出させている民族が発見されたようである。他にインドの金鉱といえば、カルナータカ州北部のハッティが有名であるが、距離が離れすぎている感がする。
ペルセポリスには、他にも、サトソトゥーン(百柱の間)と呼ばれる、百本の柱によって屋根が支えられた広間や、ダレイオス1世やクセルクセス1世の宮殿跡などが残っている。どれもことごとく崩壊しており、柱や壁が残るのみであるが、ところどころに彫刻が残っていたり、楔形文字が刻まれていたりして、往事の繁栄を偲ばせていた。
ペルセポリスはせいぜい2世紀の間の繁栄しか享受できなかったが、アケメネス朝の皇帝たちが造り出した王権の象徴たる典礼都市ペルセポリスのコンセプトは、その後十何世紀にも渡って、ペルシア語文化圏の支配者たちに強烈な影響を与えた。 その建設者については、時代を経るごとにいつの間にか、古代イスラエル王国の王スライマーン(ソロモン)や「シャーナーメ(王の書)」に登場するジャムシードとされるようになった。アパダーナには現在、12本の柱しか立っていないが、かつてはもう少し多くの柱が立っていたのかもしれない。もしくは、数に厳密な意味はないのかもしれない。この遺跡はチェヘルソトゥーン(四十柱)やハザールソトゥーン(千柱)とも呼ばれるようにもなった。
何本もの柱が立ち並び、「○柱の間」「○柱の宮殿」などと呼ばれる建物は、イランからインドにかけて、いくつもの例が見られる。イスファハーンには四十柱の宮殿があったし、デリーにもキルジー朝のアラーウッディン・キルジー(1267-1316年)やトゥグラク朝のムハンマド・ビン・トゥグラク(1300-1351年)によって建てられたカスレ・ハザールストゥーン(千柱の宮殿)と呼ばれる建物があった。デリーのラール・キラー内にある謁見の間も、別名をチェヘルソトゥーンと言う。つまり、ペルシア語文化圏の支配者たちは、自身をスライマーンのような理想の君主に祭り上げるために、実際にペルセポリスを訪れたか否かにかかわらず、多くの場合は想像で、ペルセポリスを意識した宮殿や謁見の間を造るようになった。そうでなくても、ペルセポリスには、デリーのラール・キラーまで綿々と受け継がれてきたイラン式宮殿の設計思想が感じられる。日本やヨーロッパの城が高層建築であるのと違って、イランやインドの城は概して平面的であるが、それがペルセポリスの影響だとすれば、納得が行くのである。
ところで、インドに関係する支配者の中で実際にペルセポリスを見た者がいるか、についてであるが、ティームールは1392年にシーラーズを占領しているため、ペルセポリスも見たとしても不思議ではない。ムガル朝の皇帝の中では、フマーユーンがペルセポリスを訪れた可能性が高い。実際に、フマーユーンがイランを去るとき、タフマースプ1世はペルセポリスで宴を開いたという話がある。しかし、フマーユーンは実際には一度もペルセポリスを訪れたことがなかったという話もあり、どちらが本当か分からない。
沈黙の塔
2011年の国勢調査によると、インドには57,264人のパールスィー(ゾロアスター教徒)がいる。インドの全人口の0.01%にも及ばない宗教的・民族的マイノリティーではあるが、高学歴で経済的に成功している者が多く、インドの社会では存在感を持っている。代々パールスィーによって経営されてきたインド最大の財閥のひとつ、ターター・グループが有名だ。
パールスィーがイランからインドに移住してきた経緯について、よく知られた逸話がある。16世紀に書かれた「サンジャン物語」によると、ゾロアスター教を国教としたサーサーン朝が642年にニハーヴァンドの戦いでアラブ人イスラーム勢力に破れ、事実上の滅亡に至った後、改宗を拒んだゾロアスター教徒の一団が難民となってインドへ船で向かった。彼らは各地を転々としたものの、最終的に上陸した場所が、グジャラート州とマハラーシュトラ州の境目にあるサンジャンであった。その時期ははっきりせず、8世紀とも10世紀とも言われている。
ゾロアスター教徒の一団から庇護を求められたサンジャンの王は当初、牛乳を縁まで注いだコップを提示し、「我が王国はこのコップのように一杯だ」と拒絶した。それに対し、ゾロアスター教徒の賢人はそのコップにひとつまみの砂糖を入れ、牛乳がこぼれないのを確認すると、「私たちはこの砂糖のように溶け込み、牛乳をこぼさないばかりか、牛乳を甘くします」と答えた。その絶妙な返答に感心した王は、彼らの亡命を受け入れたという。
ただし、「サンジャン物語」以外にこの出来事について触れている文献がなく、また、書かれた時期もかなり年月が経ってからであるので、信憑性は薄い。実際には、古来よりイランとインドの間で交易があり、多数のイラン商人がインドに住んでいたと考える方が普通で、サーサーン朝の滅亡は単にイラン人のインド移住を加速させただけのことであろう。
現在、パールスィーが多数住んでいるのは商都ムンバイーである。僕が住んでいたデリーにもデリー・パールスィー協会という組織があり、ゾロアスター教寺院などがあったが、デリー市民にほとんど知られておらず、パールスィーの存在感はムンバイーの比にならないほど小さい。デリーに住んでいる限り、ゾロアスター教徒に出会うことすら困難であろう。
ゾロアスター教は、「拝火教」という漢訳の通り、寺院に火を祀っている。ただ、火のみを重視しているかというとそうでもなく、彼らは火、水、風、土の四元素を聖なるものと考えている。そのため、ゾロアスター教寺院には、火の他に必ず、水があり、風を感じる糸杉が植えられ、また、土がある。そして死んだ後は、それら四元素を汚さないため、鳥葬が行われる。その鳥葬が行われる場所が沈黙の塔と呼ばれる。
インドにもパールスィーがいる以上、ゾロアスター教寺院や沈黙の塔があるが、ゾロアスター教徒以外の入場を拒否している場合が多く、今まで縁が無かった。ところが、ゾロアスター教の故地であるイランでは、ゾロアスター教関連の施設は観光地になっており、簡単にアクセスできる。ゾロアスター教を体感するために最適な場所は、ヤズドである。
ヤズドは、塩の砂漠ダシュテ・カビールと岩の砂漠ダシュテ・ルートに挟まれた砂漠の町であり、首都テヘラーンと、ホルムズ海峡に面したバンダル・アッバースのちょうど中間点に位置する。サーサーン朝下においてゾロアスター教信仰の中心地となり、多数のゾロアスター教徒が住んでいた。サーサーン朝の滅亡後も、迫害を逃れて各地からゾロアスター教徒が移住してきたために、ゾロアスター教の中心地であり続けた。現在ではイスラーム教徒が完全に多数派を占めるようになったが、人口の1割ほどはゾロアスター教徒だという。
ヤズドの中心部には、もっとも高貴な火を祀るゾロアスター教寺院がある。この火はアータシュ・ベヘラーム(勝利の火)と呼ばれており、特別な方法で作られた火だという。アータシュ・ベヘラームは世界中に9つしかなく、その内の8つはインドにあり、残りの1つがここヤズドのものだ。1500年以上前から燃え続けているが、寺院の建物自体は古くなく、1934年にインドのゾロアスター教徒の支援によって建造された。いかに、ゾロアスター教を通じて、イランとインドの関係が深いか分かる。
ヤズド・アータシュ・ベヘラームでは、糸杉に囲まれた円形の貯水湖の向こう側に、サーサーン朝風の神殿が建っており、その中に火が祀られている。初めてゾロアスター教寺院の中に足を踏み入れる。ちょっとしたホールになっており、中央部にガラスがあって、ガラス越しにアータシュ・ベヘラームを拝むことができる。金属製の杯の上に煌々と炎が燃えている。
建物の上部には、ゾロアスター教のシンボル、ファラヴァハルが掲げられていた。人の姿が見えるので、時々これを、ゾロアスター教の最高神であるアフラ・マズダーだと言う人がいるのだが、それは誤りである。ゾロアスター教では、人間は体、エネルギー、精神、意識、そしてファラヴァハルの5つで構成されているとされる。ファラヴァハルとは、人間が創造されたときに、人間の中に組み込まれた、神のエッセンスの欠片である。このファラヴァハルが、人間を常に良い方向へと導く。このファラヴァハルを図像化したのが、このシンボルなのである。例えば、このシンボルは2つの羽を持っているが、この羽は「よい考え、よい言葉、よい行動」を表している。よりよい考えを持ち、よりよい言葉を使い、よりよい行動をすることで、その羽は大きくなり、より強く、より遠くへ羽ばたける。
ヤズド郊外には2つの沈黙の塔が残っている。現在では鳥葬は行われていない。敷地内に墓場があり、ゾロアスター教徒は、イスラーム教徒と同様にここに土葬されている。ただし、遺言で鳥葬を望んだ者については、ムンバイーに送られて鳥葬されるそうだ。
やはり沈黙の塔に足を踏み入れるのは初めてであった。小高い丘の上に、壁で囲まれ、屋根のない、円形のプラットフォームがあり、中心部には穴が掘られていた。ゾロアスター教徒の死体はこの塔の上に置かれ、ハゲワシについばまれる。そして、後に残った骨などの残骸は、中心部の穴に放り込まれる。天を見上げてみても、もうハゲワシはいなかった。
ヤズドの旧市街には、狭い路地が張り巡らされた迷宮のような町並みがよく残っており、その散策も楽しい。バードギールという、家の中に風を取り込む装置が町のあちこちからニョキニョキと飛び出ている光景もヤズドの特徴らしい。2017年にヤズドがユネスコ世界遺産に登録されたことで、旧市街では観光客を受け入れるべく、急ピッチで整備工事が行われている最中のように感じた。しかしながら、町全体にはまだまだのんびりとした雰囲気が残っており、人々も素朴で、居心地のよさそうな場所であった。旧市街のそばに建つマスジデ・ジャーメも壮麗で美しかった。
愛の詩人
イスファハーン州の山中にアブヤーネという、赤色の家が立ち並ぶ小さな村がある。
2500年以上前から続く古い村で、険しい山によって外界から隔離され、村内で結婚が繰り返されてきたため、ここの住人はもっとも純粋なイラン人だとされている。話す言語もサーサーン朝時代の言語の特徴が残されているらしく、興味深い。
実は、現在イランで話されているペルシア語の発音は、インドの諸語に取り込まれたペルシア語彙を知っている者からすると、訛っているように感じてしまう。とある言語が周辺地域に伝わっていく中で、その言語の中心地では比較的早いスピードで変化が進む一方、辺縁地域では変化が遅く、その言語の比較的古い形が保存されるのは、よくあることだ。インドで使われているペルシア語彙には、それが伝わった頃の古い発音がよく残っているため、その知識でもって現代のペルシア語を見ると、違和感を感じるのである。
アブヤーネ村の看板は3つの言語で書かれている。一番上はアブヤーネ村で使われているペルシア語を表記したもの、真ん中は現代標準ペルシア語の標準的な表記法、一番下は英語である。「門」という語は、現代標準ペルシア語では「ダルウォーゼ」と発音されるが、アブヤーネ村の方言では「ダルワーザー」と発音されることが分かる。この「ダルワーザー」という発音はインドでも使われている。つまり、アブヤーネ村の方言の方が、テヘラーン方言をベースに成立した現代標準ペルシア語よりも、インドで使われているペルシア語に近いのである。
インドの諸語に多数のペルシア語彙が借用語として入っているのは、中世以来、長らくペルシア語がインド亜大陸の公用語として広く使われてきたのがその第一の理由である。13世紀以降、北インドを支配したイスラーム教徒の為政者たちは、ペルシア語を話すトルコ系・アフガン系の民族に属していた。インドの諸語にはアラビア語やトルコ語起源の語彙も少なくないのだが、これらはほぼ全て、ペルシア語に一旦取り込まれた後にインドに伝わったと考えるべきだ。
ペルシア語は、インドの宮殿や官庁で使われただけでなく、文学の媒体言語としても大いに隆盛した。インドでは、庶民の言語とは異なる高貴な言語で文学が書かれる伝統があり、それは時代を経るごとにサンスクリット語、ペルシア語、そして英語と変遷してきた。英語がペルシア語に取って代わった19世紀までにインドにおいてペルシア語で書かれた文学作品の数は、イラン本国を凌駕しているほどだ。ちょうど現在、インド人/インド系作家が好んで英語で文学作品を書き、世界各国の文学賞を取っている状況とよく似ている。
インドではペルシア語の古典文学も愛され、インド文学に影響も与えてきた。その中でも特にインド文学の小さくない一角を占めているのが「ガザル」とよばれる叙情詩の一形式である。ひとつのガザル詩は、2つ以上の詩句から成っており、各詩句は2つの半句から成る。最初の詩句は第1半句と第2半句が脚韻され、それ以降の詩句は奇数半句が脚韻する。最後の詩句には必ず詩人の雅号が入る。ひとつのガザル詩の中で、全ての詩句において脚韻は一致する必要があるが、主題は必ずしも一貫していなくてよく、詩句ごとに別々の主題へ飛ぶことも多い。むしろ、同じ脚韻からいかにあちこちに世界観を広げられるかが詩人の腕の見せ所となる。ガザルの詩形はイランで完成し、今でも人気であるが、これがインドにも伝わって、ペルシア語の他、ウルドゥー語などの現地語でも盛んに作られるようになった。
イランにおいてガザルといったら、14世紀、シーラーズに生まれシーラーズに没した詩人シャムスッディーン・ムハンマド・ハーフィズ(1315-1390年)をおいて他にいない。
「ペルシア」という地名の元になったパールス地方の中心都市であるシーラーズは13世紀、イランがモンゴル軍の侵攻を受けた際に速やかに降伏したため、破壊を免れた。さらに、ハーフィズが生きた頃のシーラーズを首都とし支配していたのはアラブ系のムザッファル朝だったのだが、その第二代皇帝シャー・シュジャーは学問を奨励したため、彼の治世(1358-1384年)のシーラーズは非常に自由闊達な空気で溢れていた。つまり、14世紀のシーラーズは非常に繁栄していたのである。そのような状況の中で生まれ育ったハーフィズは、為政者たちから才能を認められ、保護を受けながら詩作に耽ることができた。ただ、ハーフィズの生涯には不明な点も多く、一時はシーラーズを離れ、ティームールに仕えていたこともあったとされる。
ハーフィズは主にガザルで詩作をし、彼のディーワーン(詩集)には500編以上の作品が掲載されている。彼の詩の主題は、愛と酒と美である。暗喩や風刺が多く用いられ、非常に神秘的で難解な作風である。世界の各言語に翻訳されており、ドイツの文学者ゲーテにも強い影響を与えたとされる。ハーフィズはイランでもっとも人気のある詩人であり、各家庭には必ず彼のディーワーンが置いてあるという。また、ハーフィズのディーワーンの適当なページを開き、そこに書かれている詩で運勢を占う習慣もあるそうだ。

当然、ハーフィズはインドでもよく知られていた。デカン高原に興ったバフマニー朝のムハンマド・シャー2世(在位:1378-1397年)は、ハーフィズと同時代の人で、ハーフィズを宮廷に迎え入れようとしたと伝えられている。ハーフィズはその招待を承諾し、船でインドへ向かおうとしたが、途中で嵐に遭って断念したという。また、インドを代表するガザルの詩人と言えば、19世紀のデリーに生きた詩人ミルザー・ガーリブ(1797-1869年)だ。彼はペルシア語とウルドゥー語でガザルを詠んでいたが、中にはハーフィズに言及したものもあり、相当意識をしていたことが分かる。むしろ、ハーフィズの登場後、ペルシア語で詩作をしていてハーフィズに影響を受けていない者は一人もおらず、それはインドでも同じ、と表現した方がより正確であろう。

シーラーズの郊外にハーフィズの墓がある。キレイに整備された庭園になっており、六本の柱で支えられた六角形の屋根の下に、ハーフィズの詩が刻まれた大理石の墓廟が横たわっている。正直なところ、ハーフィズについては名だけを知っていて、彼の詩にはほぼノータッチだが、敷地内にあった売店でハーフィズのディーワーンを購入し、読み始めているところである。
シーラーズには、ハーフィズと並び称される詩人サアディーの墓もある。だが、こちらは時間がなかったために行けなかった。
最後に:イランで考えたこと
米国から「悪の枢軸」と名指しされ、度々制裁も受けてきたイラン。日本人の目からすると、北朝鮮などと協力しながら核開発やミサイル開発を行っている疑いがあり、気になって仕方がない。ちょっと昔の話では、東京の上野公園などでせっせと偽造テレホンカードを売っていたのがイラン人であった。日本と同じく地震大国であり、大地震に見舞われると被害の様子が日本にも入ってくる。残念ながら、日本のメディアにイランの国名が好意的な文脈で登場することは非常に少ない。
1978年のイラン革命後、イランはイスラーム法に則って統治の行われる国となった。特に女性の服装には厳しくなり、女性は布で頭を覆って髪の毛を隠さなければならず、この規則は外国人観光客にも適用される。テヘラーンへ向かう飛行機の中では、着陸時間が近づくと、女性たちがそそくさとショールなどを頭に巻き始める。町には風紀警察がおり、女性の服装をチェックしているという。そのような情報だけを聞くと、どれだけ厳格なイスラーム国家だろうと想像してしまう。
ところがイランは全く垢抜けた国であった。確かに女性たちは頭部を布で覆ってはいるが、髪の毛1本見せないような細心の注意が払われているわけではなく、むしろそれは髪を引き立てるファッションの一部として取り込まれ、感覚としては髪飾りのようなものであった。町を歩く限りでは、女性たちが抑圧されているような様子は見られず、むしろファッショナブルな人が多い印象で、ヨーロッパの街角とそれほど変わりはないように思われた。制裁の影響で物資が不足しているかとも思ったが、市場は物で溢れており、困窮している様子は見受けられない。コカコーラは入って来ないはずだが、海賊版「オリジナル」コカコーラが流通していて、気軽に飲むことができる。テヘラーンの市街地では多少の乞食に出会ったが、普通の国の範囲内だ。イスラームの国なので酒屋は一切なく、レストランでも酒類は一切出ない。ノンアルコールビールとして売られている飲み物はピーチ味やレモン味の炭酸飲料だ。しかしながら、ガイドの話によると、闇ではあらゆる酒類が手に入るという。前述の通り、いくつかのSNSにアクセスが制限されているが、VPNを使えば簡単にアクセスできる。どの国にも表と裏があるが、裏の部分でイランは至って普通の国であった。
イスラーム教は偶像崇拝禁止とされているが、イランでは、モスクも街も偶像だらけであった。人物や自然を絵や彫刻にして表現する営みは、ペルセポリスの遺跡を見れば分かる通り、イスラーム化以前のイラン人が誇りを持って行ってきたことである。イスラーム化した後も、彼らはイスラーム教を自分たちなりに解釈して、折合をつけながら、受け入れてきたように思われる。ただし、それをスンナ派とシーア派の対立に結びつけて考えるのは早計であろう。なぜなら、現在でこそイランはシーア派イスラーム教徒が多数派を占める国であるものの、元々はスンナ派の国だったからだ。イラン人の多くがシーア派になったのは16世紀のサファヴィー朝以降である。それ以前に造られたモスクなどにも偶像が見られるので、シーア派であることと偶像とは関係ないと考えるのが妥当だ。むしろ、イラン人が自身の美的センスを実現するために、図像的な表現方法は欠かせなかったと考える方が、短い間だけイランを旅しただけだが、正しいように思えた。
ウズベキスタンでも、絵の入ったモスクやマドラサ(神学校)をいくつか目にした。サマルカンドのシェールダール・マドラサやブハーラーのナーディル・ディーワーンベーギー・マドラサなどである。当地では、偶像崇拝禁止のはずのイスラーム教の宗教施設にわざわざ偶像をモチーフにしたのは、「支配者が自分の権力を誇示したかったから」などと様々な理由が付けられていたが、イランを旅行してみると、モスクやマドラサに絵が入るのはごく普通のことであった。そしてそれはインドでも同様である。
偶像だけでなく、毎日の礼拝についても、イランのイスラーム教は緩かった。礼拝を呼びかけるアザーンは時々聞こえて来るが、他の国ほど、町の人々をうるさく礼拝にかき立てていなかった。モスクへ行っても、熱心に礼拝している人はほとんど見なかった。日本の神社仏閣とそんなに変わらない雰囲気だった。レストランのメニューに豚肉のメニューは見当たらなかったが、普通に豚肉も食べられているのではないかと思われる。
元々アラブ人の信仰だったイスラーム教が世界宗教として脱皮できたのは、その拡散の過程で、イラン人のような他民族が適当に力を抜いて受容をしたからではなかろうか。特に中東以東の文脈で言えば、イスラーム教は、イランもしくはイラン人というフィルターを通して、中央アジアに伝わり、さらにインドにも伝わった。インドのイスラーム教もかなり自由であるが、イランに来てみてその理由がよく分かった気がする。もし、アラブ人がインドを支配し、イスラーム教を直接伝えていたら、インドのイスラーム教は、もっと違ったものになっていたに違いない。
インドは、イランから受け取ったものが非常に大きいので、インドへの愛情を通して、イランには言い知れない憧れを抱いていた。偉大なるペルシア文明の正統な後継者として君臨する誇り高い国と、勝手に想像を膨らませていた。しかし、イランの歴史を改めてひもといてみると、現在のイランの地がイラン系民族の国であり続けたわけではなく、アラブ人やトルコ人の支配を受け、西欧列強に翻弄されてきた。イラン系民族という系統で言うならば、中央アジアやアフガニスタンにもイラン系民族は散らばっており、現在でもタジキスタンのようなイラン系民族の国家が存続しているし、ペルシア語やペルシア語文学という文脈で考えるならば、それらの地にインドなどを加えた、かなり広い範囲でその発展を追っていく必要に迫られる。つまり、「イラン」というアイデンティティーもかなり複雑なのである。
基本的には世界遺産を中心とした観光地巡りをしただけなので、イランが誇る建築の数々を見てきたのだが、それらも、イランの地で独自に創り上げられたものではなく、外部からの影響を受けながら発展してきたものだった。素人目で見ても、モスクのタイルの使い方など、明らかにティームール朝の建築の影響が見て取れた。ティームールはインドに侵略した際にインドのモスクなどに感動し、大工や職人を連れ去ったので、それにはインドの影響がある。そしてタージマハルをはじめとしたムガル朝の建築は、イラン建築の影響が色濃い。そう考えてみると、これらの地域の建築は互いにグルグルと影響を与え合っており、完全なる源泉は存在しないことが分かる。
もっとも、大陸の国々の歴史はどこも多かれ少なかれ似たようなものであろう。日本列島がたまたま四方を海で囲まれ、同一王朝、同一民族による統治を長年維持できたために、日本人はどうしても歴史、言語、アイデンティティーなどをシンプルに捉えてしまいがちだ。それは、世界の歴史の中では、例外的に希有なことだと、改めて気づかされる。
イランの食事については、インド料理からスパイスを引いたような感じの料理が多かった印象だ。全体的に味付けが薄く、どれもすんなり食べられる味だった。辛い料理はなかった。正直に言えば、もっとスパイスを効かせたらさらにおいしくなるのに、と感じた。
これについては、むしろトルコの影響を考えた方がいいだろう。イランもインドもトルコ系の王朝に支配された時期が長くあり、その時期にトルコ料理の影響を受けた。トルコ料理にインド原産のスパイスが加わったものがインド料理ならば、イラン料理はトルコ料理にイランの土着の食文化が融合してできたものに違いない。
イラン料理の主食は、ナーンなどのパン類もしくはご飯で、肉料理や野菜料理と合わせて食べるのが基本的な構成だ。インドのダール、日本の味噌汁に当たるような豆のスープも定番料理としてあった。外れがなかったのが、チェロー・キャバーブと呼ばれる、ご飯とロースト肉がセットになった料理だ。飲み物は、ドゥーグと呼ばれるヨーグルト飲料がおいしかった。なお、インド料理は基本的にパーティー料理なので、テーブルを囲んだ人々で複数のカレーを取り分けて食べるのが普通だが、イラン料理はどうも個人個人にセットで出される定食系料理という感じがした。
イランのビリヤーニーには驚いた。インドでは、ビリヤーニーと言えば、パエリアのような炊き込みご飯であるが、イランのビリヤーニーは、ルーマーリー・ローティーのような薄っぺらいパンに肉が包まれたものであった。つまり、全く異なった料理であった。
インドと同じくチャーイを飲む文化がイランにもあり、街中にはチャーイハーネと呼ばれる伝統的な茶屋がある。ただ、コーヒーも普及しつつあるようで、観光地を巡った限りでは、カフェの方が目立った。イランのチャーイはハーブティーがおいしく、カクテルのように様々なハーブの組み合わせが楽しめた。イランの喫茶店では、ナバートと呼ばれる、棒に氷砂糖を付着させたものがよく添えられていた。これをチャーイに浸してかき混ぜると砂糖が溶けて甘くなるというわけだ。これは優れ物、ということで、サフラン入りナバートをお土産として購入したのだった。ちなみにナバートはイスファハーン発祥とのことである。
イラン人はとてもフレンドリーかつ紳士的だった。インド人のようにせっかちではなく、節度をもって人と接することのできる人たちだと感じた。観光地の土産物屋も良心的で、買うまで帰さないとか、百倍の値段を吹っかけるとか、その種の悪徳商売は、幸運だっただけかもしれないが、ついぞ体験しなかった。テヘラーンのラッシュアワーは酷い渋滞で、カオスな状態も散見されたが、だからといって手当たり次第にクラクションを鳴らしまくるような迷惑な人はおらず、基本的に落ち着いていた。
今回のイラン旅行は、家族旅行という形を取ったため、いろいろ制約もあった。歴史と見所に満ちた国なので、時間無制限で心ゆくまでバックパック旅行したら、面白い国のひとつであろう。イスファハーンにもっと長く滞在して、マイナーな遺跡や路地裏の奥の奥など、隅々まで見てみたかったし、ヤズドにもっと長く滞在して、迷宮のような旧市街を歩き回ってみたいと思った。
しかしながら、インドの周辺国家を順に旅する内に、インドほど面白い国はない、という思いも次第に強くなっていっている。あれほど強烈で、あれほどユニークな国が他にあるだろうか。常に油断ならないが、単なる移動も日常の買い物も、時としてひとつの物語になってしまうほど、毎日が退屈しない。インドに慣れてしまうと、どの国へ行っても、人生観を覆されるようなカルチャーショックを感じる機会がなかなか巡って来ない。あのような国で人生の10年以上の時間を過ごせたのは幸運なことだったと、今更ながら思う。そんな、イラン旅行であった。






































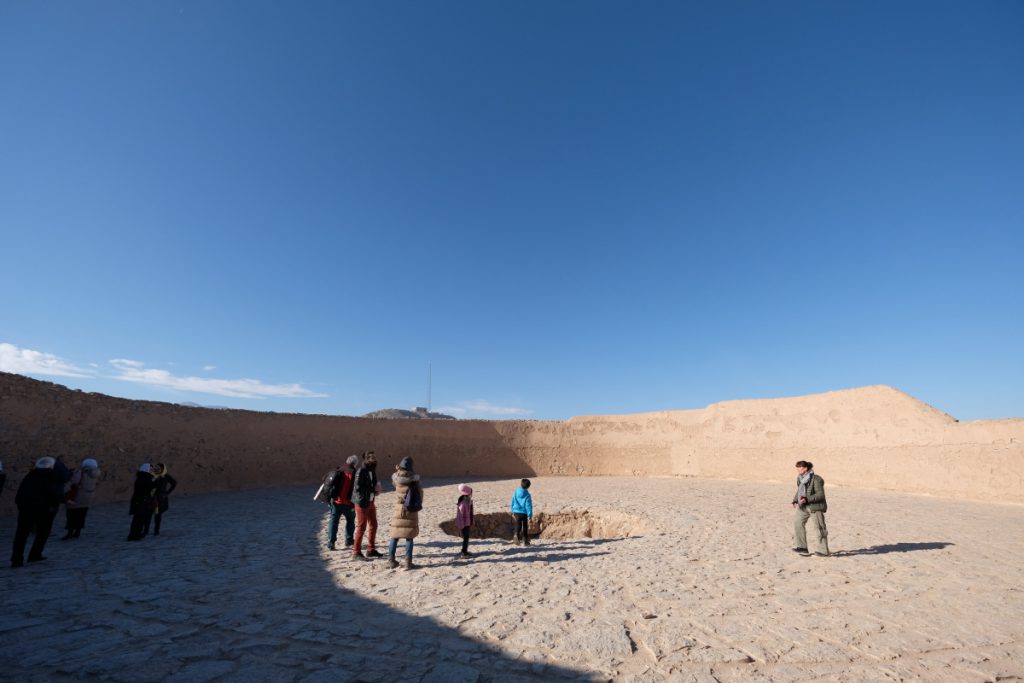


















welcome back that ‘koredeindia’
i’m very satisfied you’re energetic for the history in asian countries, also
addicted to india you escorted me before.
it’s not boring at all that i read your long report.
when you were in iran, my son-in-law was in russia 3 weeks .
i’m not that miura yuuichiro, not tough.
i’m happy to read your adventure report anyway.
spaceboo…
これでインディアの記事から一つ聞きたいことがあるのですが、ここから質問もしてもいいですか?
前に読んだ記事のなかで、南の小さな村に先進的な学校があり、そこには先生がいなく十代の子供達が共同生活をしていて人生で必要なことをその学校から学ぶみたいなことが書いてあったのですが、その村の名前を教えてもらえませんか?記事を探したのですが出てこなくて…。もし間違っていたらすみません。
コメントありがとうございます。おっしゃっているのは、チャッティースガル州などの部族の習慣であるGhotulのことだと思います。若い男女が共同生活をして部族のしきたりなどを学び合うものです。特定の村のことではありません。「Ghotul」で検索していただければ、いろいろ情報が出て来ます。とりあえずWikipediaのリンクを貼っておきます。
https://en.wikipedia.org/wiki/Ghotul